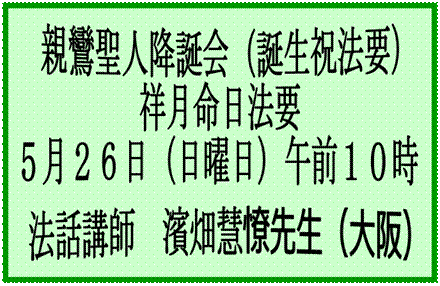 不思議なもので、歴史研究は時間が経つほど新しいことが発見されていくようです。資料が失われることはありますが、資料が新たに見つかることもあります。過去には定説となっていたものがくつがえされ、新説が立てられることはごく当たり前のことのようです。
不思議なもので、歴史研究は時間が経つほど新しいことが発見されていくようです。資料が失われることはありますが、資料が新たに見つかることもあります。過去には定説となっていたものがくつがえされ、新説が立てられることはごく当たり前のことのようです。
宗祖親鸞聖人やその周辺についても同じことが言えます。これまで歴史的な親鸞聖人を知る手がかりとして重要視されてきたものの一つに、聖人のひ孫である覚如上人が書かれた『御伝鈔ごでんしょう』があります。これをお読みくださっている方の中にも、親鸞聖人在世当時の様子を描いた絵などをご覧になったことのある方もいらっしゃると思います。例えば、流罪先の越後での苦しい生活の様子や、常陸稲田の草庵での隠居されたかのような様子を描いたものです。これらは主に覚如上人のお言葉を元に想像して描かれたものですが、最近の研究では生活状況はだいぶんと違うようだということが分かってきました。
親鸞聖人が越後に流される一ヶ月前に、聖人の叔父であり関白九条兼実と後鳥羽上皇に仕えた日野宗業は越後の権介(国司)に任命されています。これは地方の副長官的な役職であり非常に高い地位です。聖人が越後流罪に処される直前に、後鳥羽上皇によって宗業が越後国司に任命されたことは偶然とは考え難いことです。また、親鸞聖人の奥方であった恵信尼さまの父三善為教は九条兼実に仕えた元越後の介すけでしたので、越後には領地(
荘園) を所有していました。そのため、聖人は三善家の領地内で生活されていたと推測されます。
このように親鸞聖人が越後の地に流されたことには背景があったと考えられ、越後での生活は従来考えられていたような不自由な生活ではなかったと考えられます。
さらに許されて後に親鸞聖人家族が赴いた常陸の地には、恵信尼さまが幼少の頃から仕えたと考えられる九条兼実の娘任子(宜秋門院、後鳥羽天皇の中宮)の荘園があったので、聖人夫妻にとって全く縁もゆかりもない土地で生活をされた訳ではなかったのです。
聖人が草庵を結ばれた稲田には神社(大社、中社、小社の三階級がある)の中でも特に有力な神格である明神大社に位づけられた稲田神社があり、かなり栄えていたことが分かります。稲田の草庵はこの稲田神社の境内地もしくは門前近くにあったと考えられています。すると、稲田の草庵は門前町としても宿場町としても栄えていた場所に構えられたものでした。ですので、草庵にこもって隠居生活をし、戸を閉め人に会わず執筆活動をしていたとは考えにくいのです。もしもそのような生活を望まれるならば稲田ではない場所を選ばれていたはずです。
このようにして、研究が進むとかつてとは違った親鸞聖人の生活が見えてきます。しかし、それによって親鸞聖人が伝えてくださった浄土真宗の教えが変わるという訳ではありません。
聖人が伝えてくださった浄土真宗の教えは「念仏の教え」です。「行住坐臥、時節の久近を問わず」(何かしているときも、何もしていないときも、座っているときも、臥しているときも、いつでも)南無阿弥陀仏のお念仏を申し、阿弥陀さまから私にかけられている慈悲を味わい、阿弥陀さまに自身の生き方を確認する生き方をするという教えです。どのような生活環境であろうと、どのような健康状態であろうと、「お念仏を申すこと」を中心とする生き方ですので、親鸞聖人の生活環境が研究の進む中に明らかになり以前とは異なる事実が出てこようとも、聖人の伝えてくださった教えが揺らぐことはありません。親鸞聖人は真実の世界と誠の生き方を浄土真宗の教えを通して教えてくださいました。
聖人の誕生は一一七三年五月二十一日だったと言われていますので、五月には聖人の誕生を喜びお礼申し上げる降誕会(ごうたんえ)をお勤めします。ご講師は大阪より濱畑慧憭先生をお招きします。ぜひ、お参りください。

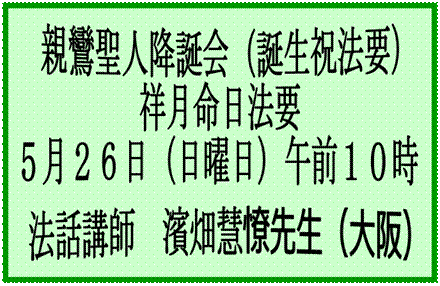 不思議なもので、歴史研究は時間が経つほど新しいことが発見されていくようです。資料が失われることはありますが、資料が新たに見つかることもあります。過去には定説となっていたものがくつがえされ、新説が立てられることはごく当たり前のことのようです。
不思議なもので、歴史研究は時間が経つほど新しいことが発見されていくようです。資料が失われることはありますが、資料が新たに見つかることもあります。過去には定説となっていたものがくつがえされ、新説が立てられることはごく当たり前のことのようです。
